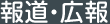新しい評価基準である
技術士コンピテンシーによる初めての試験が終わりました。予想どおりだったところもあれば、意外な問いに驚いたりと、とても興味深い2日間を過ごしました。その後1週間にわたって連載した試験問題の振り返りもひと段落しましたので、ここで次年度試験に向けての講座を開講することにいたします。
わたしの講師としての活動は、平成22年度試験に合格した翌年からSUKIYAKI塾の添削講座に参加するかたちでスタートしました。
SUKIYAKI塾のほか、身近な知り合いを含めると、これまでの9年間でのべ180名ほどのかたたちに指導アドバイスしたことになります。そしてその一助となったかどうか、平成30年度試験までの8年間で46名のかたが合格されました。
また、平成27年度からは総監の指導アドバイスも開始したところ、初年度にもかかわらず6名ものかたから吉報をいただくことができました。わたしはあくまで触媒にすぎませんが、『総監合格』にいくらかでも貢献できたであろうことに我ながら驚いています。
SUKIYAKI塾の活動と平行して綴り始めたこのブログですが、平成26年ごろからブログを訪問してくださるひとが増え始め、それに比例するように添削指導の依頼をあちらこちらから受けるようになりました。そこで平成28年から独自の添削講座を開講して受験に真剣に取り組む方のサポートを始めました。
軌道に乗った平成29年度以降、多くの受講生の皆さんとメールによる濃密なやりとりができました。受講生に恵まれたことが大きいと感じていますが、受講生の皆さんの理解の度合や伸び具合がそれはとても良い感触でした。
受講者さんから試験本番の感想を頂きました。
【総監】
●試験がようやく終わりました。論文については、ヒューマンエラーについての記載でした。文章は何らか記載できましたが、評価は・・。かな?私の現時点で出来ることはしたので、後は結果を待つのみです。これまで、指導ありがとうございました^_^。
●日曜日に総監を受けてきました。記述はなんとか五枚を9割りがた埋めることができました。特にはじめは今回の添削の内容をほぼ使うことができたので、考える余裕ができました。ありがとうございます。これで予定の50パーセントは獲得できたと思います。しかし、択一が23~26のできなので、あともう少しだったと思っています。来年はオリンピックもあるので、総監に専念して望みたいと思います。ご指導をありがとうございました。
【建設環境】
●試験終わりました。必須はまぁ書けました。選択は難しかったです。3はなんとか埋めましたが、手応えがありません。2-1と2はほぼ書けませんでした。約半年間色々とご指導をありがとうございました。
●本日、建設環境の筆記試験を受験して参りましたので、試験問題をお送りいたします。必須や専門のⅢでは、最も重要な課題に対する複数の解決策と、それらの解決策に共通するリスクと対策法について問われました。専門のⅡ-2では、これまでのアセスそのものの設問がなくなり、特にⅡ-2-2では、業務経験がないと対応が難しかったという印象です。全問、ほぼ100%埋めることができましたが、新傾向の部分にはどれだけ題意に沿えているのか、自信がないです。昨年のほうが手応えはあったような気がします。以上、速報でした。これまで半年間、ご指導、ありがとうございました。
●本日の筆記試験、なんとか、とりあえずは全ての問題を無事書ききることができたので、取り急ぎお礼と報告をさせていただきます。以下は個人的なご報告ですので、読んでいただけなくとも構いません・・問題は、Ⅱ-2の自主アセス以外は全て、添削で指導いただいたものにアレンジを加えた内容で対応できました。Ⅰは防災、Ⅱ-1は多自然川づくり→生態系ネットワークで書いた課題のアレンジで対応しました。(個人的には手応えありでしたが、そういう時ほど落ちているという声もよく聞きますが・・)ただ、Ⅲでは社会資本整備事業の方を選んだのですが、、(略)・・・と、思っています。しかし、あの瞬間ほかに解答を作成する技量は自分にはなかったので、そういう意味では今ある力でとりあえず悔いなくできたかなと思います。合格ラインに到達できたかはわかりませんが、とにかくご指導のおかけで試験本番乗り切れたと思っております。勝手なメールでかなり長くなってしまいましたが、また10月末に結果のご報告だけでもさせていただければと思います。以上、ありがとうございました。
●15日の技術士試験を無事に終えてきました。今年もお世話になった御礼をメールしようと思いつつも、技術士試験の後、すぐに長期出張だったので落ち着く時間がありませんでした。今年は試験形式が変わりましたが、これまで繰り返し添削してきていただいた、積み重ねてきたことが十分に出せたと感じています。とても完璧とは言えませんが、手ごたえがあります。もちろん、まだ結果は分かりませんが、自信をもって本番を望めたこと自体、ここで添削し続けてもらったおかげだと思っています。(なぜなぜ分析やボトルネック抽出、技術者としての技術力アピール等、とても役に立ちました)今年は、結果発表に向けて前向きに、復元論文や面接対策も進めようと思います。今年こそ、10月29日によい結果報告ができたらと思います。それでは、また。
【河川砂防】
●報告が遅くなりましたが、試験を終えてきました。一般は、・生産性向上・国土強靭化であり、想定範囲内の出題内容でした。しかし、問われ方が、(3)までは、河川砂防の問題Ⅲと同じ設問、(4)で倫理(略)、社会の持続可能性(略)であり、回答用紙に収めるのに苦労しました。バランスの悪い字数の記載となりましました。この一般問題で、テンションダウンです。しかし、午後の専門は、すごろく様のアドバイス通り、栄養ドリンクを飲んで、昼休みに添削指導頂いた内容をレビューしたところ、・1枚ものの出題内容は、過去問通り、・2枚ものも出題内容は、過去問通りで、設問を変更。以上は、一応、記載しました。しかし、問題Ⅲで(略)どうも、(2)で(1)の課題のうち1つについて複数の解決策(3)で複数の解決策に共通したリスクと対策になじめませんでしたが、一般ほどの苦労はしなかったと思います。結論としては、一般と問題Ⅲの出来が合格に左右されると思います。ご指導を受けたにも拘らず、反映できずに、申し訳ありません。問題を送るのが、これまでご指導頂いたことへのお礼ですが、それは、明日、対応させて頂きます。
【環境部門自然環境保全】
●連絡遅くなり、申し訳ありません。試験が終わり、ようやく落ち着いてきました。改めまして、この度は、ご指導ありがとうございました。添削、指導をいただくのが勉強のモチベーションになっていました。試験は、一応、全ての問題で全てのマスを埋めました。出来ですが・・・、微妙なラインかなと思っています。必須は、SDGsを選択しました。環境部門に関係のある5つの目標について問われたのですが、(1)、(4)が用意不足でざっくりとしか答えられずでした。専門Ⅱは、1は自然環境保全地域を選択、2は域外保全を選択し、これは自信を持って回答できました。専門Ⅲは、地域戦略を選択しました。(1)の課題の抽出と分析について考えてしまい、時間がなくなり、焦って、題意に沿った回答ができてないような気がしています。一応全マス埋めましたがどのくらい点数をもらえるかと思っています。正直、緊張してしまいました。結果が出るまでは、口頭試験の準備をしようと思います。ダメだったら、悔しいので、また一からやろうと思っています。重ね重ねですが、この度は本当にありがとうございました。
などの報告をいただきました。
総監は順当な出題だった印象ですが、総監以外部門のほうはほぼ予想どおりの出題テーマに対して、細かい設問、特に必須科目Ⅰや選択科目Ⅲの問い方の変化に翻弄されている様子が生々しく描写されていますね。試験が終わったいま読んでも「頑張れ!」と手に力が入ってしまいます。
そして早くも次年度試験対策講座への問い合わせもいただいています。ありがたいことにブログの読者にお尻を叩かれここにようやく準備が整いましたので、ただいまより令和2年度試験に向けての添削講座を開講いたします。
これまでの指導経験を注力しますのでお任せください。
そのほか筆記試験再現論文に対するコメント評価も行います。
先日の試験答案について第3者の視点からの評価を欲しているかたはぜひどうぞ。
本サービス(添削指導アドバイス)はSUKIYAKI塾とは異なり有料でお受けします。
対象とする技術部門科目は以下の2つです。
●建設部門建設環境
技術士受験指導の経験は早いもので9年、そして建設環境分野の技術者としての業務経験は24年になりました。これまで主に沖縄県内での環境調査、環境影響評価、自主アセス(ミニアセス)に携わっております。
わたしの専門はどちらかというと自然環境に関する分野ですので生活環境の保全に関する現場感覚はやや劣るかもしれません。しかしながらこれまで添削するうえで支障はありませんでした。
また、他の部門科目(例えば環境部門など)についてもご希望であればお引き受けします。ただし専門技術に関する指導はできませんので論理構成や文章に関する指導アドバイスとなります。
なお、これまで建設環境以外には、河川、砂防及び海岸・海洋の環境寄りのかた、環境部門の環境保全計画と自然環境保全、水産部門の水産資源及び水域環境のかたを指導いたしました。
●総合技術監理部門
総監については科目を問いません。ただし建設-建設環境以外の科目の場合には専門技術を踏まえた管理については言及できないこともあります。
なお、これまで建設環境以外には、施工計画・施工設備及び積算、道路、都市及び地方計画、河川砂防・海岸海洋、土質及び基礎、上水道及び工業用水道、農業土木、環境保全計画、自然環境保全のかたを指導いたしました。
ご希望のかたには、平成29年2月23日で頒布が終了した「技術士制度における総合技術監理の技術体系(第2版)」(いわゆる青本)のテキストデータを差し上げます。
なお一部内容を法律等の改正に伴い書き換えています(ただしH29年時点までのものです)。
下記の5つのコースを設けました。
※併願・重願の場合はそれぞれの部門科目単位で受け付けます。
★お申込みはこちらからお願いします
お申込みフォーム
①令和元年度筆記試験の再現論文に対するコメント評価
内容:再現論文のコメント評価を行います。建設環境は必須科目Ⅰ、選択科目Ⅱ-1、Ⅱ-2、Ⅲの合計4つ、総監は記述論文(必須科目Ⅰ-2)です。
原稿に赤を入れるのではなく、メールでコメントをお返しする方式です。
返信回数:各問題に対し、1回のコメントとそのコメントを受けての再質問・返信を1回の計2回
料金:3,000円
【令和2年度試験対策】
②出願書類作成コース
期間:受付完了時から令和2年度試験の申込期限日7日前の4月13日(月)まで書類を受け付けます。
※令和元年度技術士第一次試験再試験の合格者で、受験資格を満たすひとについては5月1日(金)まで。
内容:受験申込書の記載内容と業務経歴票(5行の業務経歴と「業務内容の詳細」)についての添削指導を行います。令和2年度の様式が正式発表されるまでは令和元年度様式で添削指導を行い、令和2年度様式が発表され次第、あらためて添削指導いたします。
うまく作成できないかたには業務経歴のたな卸しと詳細業務の骨子の作成アドバイスからスタートします。
添削回数:期間内は回数無制限です。ただしわたしがOKと判断したらそこで終了とすることもあります。
料金:15,000円
③筆記試験論文添削 長期コース(7~11カ月)
期間:受付完了時から令和2年度筆記試験日7日前まで論文を受け付けます。総監部門は7月4日(土)まで、その他部門は7月5日(日)までです。
内容:建設環境については必須科目と選択科目を、総監については記述論文(必須科目Ⅰ-2)の添削指導を行います。過去問題に対する回答論文の添削です。原稿に赤を入れるのではなく、メールでコメントをお返しする方式です。
論文の仕上がり具合に自信がないかた、文章作成が苦手なかた、論理的思考が苦手なかた、専門技術分野が偏っているかた、それぞれに応じた指導をいたします。
添削回数:期間内は回数無制限です。ただし複数の論文を同時並行では添削しません。わたしが次の問題に移ってOKと判断してから別の設問に取り組んでください。
料金:30,000円 (平成31年度の筆記試験論文添削コースを受講したかたで同部門同科目の場合は25,000円)
④筆記試験論文添削 中期コース(3~6カ月)
期間:令和元年12月下旬頃から受付を開始します。受付完了時から令和2年度筆記試験日の7日前まで論文を受け付けます。総監部門は7月4日(土)まで、その他部門は7月5日(日)までです。
内容:建設環境については必須科目と選択科目を、総監については記述論文(必須科目Ⅰ-2)の添削指導を行います。過去問題に対する回答論文の添削です。原稿に赤を入れるのではなく、メールでコメントをお返しする方式です。
論文の仕上がり具合に自信がないかた、文章作成が苦手なかた、論理的思考が苦手なかた、専門技術分野が偏っているかた、それぞれに応じた指導をいたします。
添削回数:期間内は回数無制限です。ただし複数の論文を同時並行では添削しません。わたしが次の問題に移ってOKと判断してから別の設問に取り組んでください。
料金:20,000円
⑤筆記試験論文添削 短期コース(1~2カ月)
期間:令和2年4月末頃から受付を開始します。受付完了時から令和2年度筆記試験日の7日前まで論文を受け付けます。総監部門は7月4日(土)まで、その他部門は7月5日(日)までです。
内容:建設環境については必須科目と選択科目を、総監については記述論文(必須科目Ⅰ-2)の添削指導を行います。過去問題に対する回答論文の添削です。原稿に赤を入れるのではなく、メールでコメントをお返しする方式です。
論文の仕上がり具合に自信がないかた、文章作成が苦手なかた、論理的思考が苦手なかた、専門技術分野が偏っているかた、それぞれに応じた指導をいたします。
添削回数:期間内は回数無制限です。ただし複数の論文を同時並行では添削しません。わたしが次の問題に移ってOKと判断してから別の設問に取り組んでください。
料金:15,000円
【注意事項】
●本サービスは、Gmailを使用して行いますので、Gmailの送受信が可能な環境であることが必須条件です
●本サービスに使用するファイル形式はPDFもしくはMS Wordファイルのみです。これ以外のファイルは原則として対応できません
●添削指導の対象である経歴票や論文等はメールに添付してお送りいただきます
●メール受信後、添削コメント等を返信するまでに最大4日間の日数をいただきます
●総監については科目を問いませんが建設-建設環境、水産-水産資源及び水域環境以外の科目の場合には専門技術を踏まえた管理については言及できないこともあります
●領収書は発行いたしません
●振込手数料はご負担ください
本サービス(添削指導アドバイス)をご希望されるかたは上記の内容を確認いただいたうえで下記のフォームにてお申込みください。お申込みの時点で上記の注意事項に同意いただいたものとします。
フォームを受信後、遅くとも翌日中には振込先の銀行口座をご案内するメールをGmailで返信いたします。
※3日以上経過しても返信がない場合はGmailとのやりとりが不可能な環境と思われます。その際はお手数ですがご自身で設定等を調整したうえで再度ご応募ください。
★お申込みはこちらからお願いします
お申込みフォーム