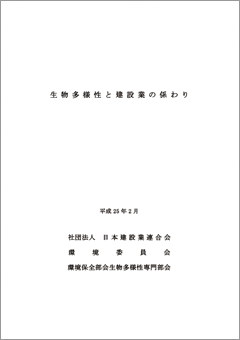筆記試験に合格されたみなさん、おめでとうございます!
ここまできたからには勝利の栄冠をつかみ取るべく、このまま最後まで突っ走ってください!
お祝いマカロン【DALLOYAU自由が丘店】
発表当日は朝の6時前(5時50分頃)に日本技術士会のサイトにPDFがアップされましたね。
夜中の0時過ぎにまだ発表がないことを確認して就寝、ちょうど6時前に目が覚め、枕元のiPhoneで確認したところまだ発表がなく、今年は遅いなぁともう一回リロードしたらアップされてました。
今年はSUKIYAKI塾の添削講座をやっていないし、そのほかの知り合いの番号も知らないので、口頭セミナーの需要予測もかねて沖縄の那覇試験会場(G)をチェックしていったらなんと7人も合格していました、建設環境に。例年4~5人ですからね。
それにしても環境部門の那覇会場の合格者は部門全体をみても自然環境保全に1人だけ、なんですからこれには驚きました。
今年の合格発表というか成績の通知ですが、一般部門はⅠ(択一)、Ⅱ(専門知識と応用能力)、Ⅲ(課題解決)のそれぞれの成績があって、さらに全体の結果(合否)が示されていましたね。
しかもⅡとⅢで両方がAなら文句ナシですが、わたしのまわりには、ABで合格のひともいれば、BAで不合格など、ボーダーライン上のひとがとても多いことが判明しました。
こうやって細かく評価されると、合格にしろ不合格にしろ、今後の対策がより立てやすいですね。
これから全国各地で口頭試験対策セミナーが開催されます。
ここ沖縄でもやりますので、お近くのかたはぜひ受講されてください。詳しくは
こちら
また、SUKIYAKI塾に限らず職場の技術士のかたなどにも模擬面接等をお願いして、試験までには複数回の模擬面接を受けるようにしてください。
今年からは試験時間も短いですし、この面接自体の場馴れ具合が大きく響くと思いますよ。
それから、選択科目ⅢがBで合格されたかたは、再現論文を作成して、さらには資料を駆使して模範解答を作成して、技術士に添削をうけるなどのフォローをしてくださいね。
B判定となった部分に関しての質問がほぼ確実に来ると思います。
ここでA評価にふさわしい返答ができなければ不合格はまちがいないでしょう。
口頭試験まで進んでの最終的な「不合格」は、想像して余りある壮絶な辛く悔しい経験となるようです。
これは脅しではありませんですよ。
最後に残念な結果となったかたへ
来年の試験まで、もう1年もありません。
9か月ですよ、9か月というのは半年と3カ月です、1年の3/4です。
いまから取り組むのに一番いい教材が、ご自分の再現論文です。
さらに資料を駆使して模範解答を作成しましょう!
そして経歴票と小論文をもういちど見直しましょう。
特にあわてて提出したひとは、来年こそは練り上げた経歴書を提出しましょう!