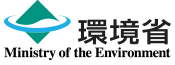早いもので3月の最終週となりました。
年度業務の完了検査もピークを過ぎたあたりでしょうか。
部署の移動や転職に独立、退官・退職など、働きかた、社会との関わりかたに大きな変化が訪れる季節でもあります。
いろいろなお立場があると思いますが、抱えている業務を最後にピシっと〆て、4月からの新しい生活、業務、課題に取り組んでください。
そして技術士試験を受験されるかたへ繰り返しのお知らせです。
今週末の4/1(金)から受験申込書の配布が始まります。
書類の受付は4/27(水)までです。
あとひと月しかありませんので、経歴の棚卸、代表業務の詳述については悔いのないように。
春といえば桜ですが、今年は開花が早いようですね。
わたしは4月に南関東あたりに出張する予定があるのですがどうやら満開は過ぎてしまいそうです。
残念ですが桜のほかにもいろんな花がいっせいに咲きますし、新芽も芽吹きますから、そういった新しい生命の息吹に触れることを楽しみにしています。春はいきものが活発になりますからね。
身近なところでは池や田んぼなどの水辺でも春を感じることができます。
気温が上り、それにつられて水温が上昇し、さらに日射量も増加すると、ある日突然に水の色が変わりますよね。いわゆる春のブルーム(スプリングブルーム)です。
これの規模が極端に大きいものが内湾やダムなどの閉鎖性水域で発生する植物プランクトンの大増殖です。
春になって水温があがると表層の水と下層の水がぐるぐる循環を始めて水底あたりに溜まっていた窒素やりんなどの栄養塩類が表層あたりまで上がってきます。
そうすると冬の間はあまり活用されていなかった栄養塩類が日の当たる表層をも満たすようになるわけですから、ここで暖かい日差しをいっぱいに受けた植物プランクトンが爆発的に増え、増えすぎるとアオコや赤潮などの人間生活に多大な負の影響を及ぼす事態が引き起こされる、というわけです。
その原因(のひとつ)が陸域からの過剰な栄養塩類の流入によるわけですから、これまでは環境基準などを設定することでその抑制を図ってきました。
しかしそもそも環境基準というのは「濃度」に対する基準であったわけで、それでは・・・・・
続きは「Ⅰ 総量規制基準の位置づけ」を読んでください。
閉鎖性水域の問題は定期的に出題されていますので、しっかり理解しておいてください。
ヒカリモのブルーム【西表島】
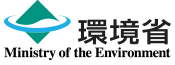 報道発表資料
平成28年3月25日
報道発表資料
平成28年3月25日
水・土壌
「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」(総量規制基準専門委員会報告案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
中央環境審議会水環境部会総量規制基準専門委員会では、「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」(総量規制基準専門委員会報告案)をとりまとめました。
本報告案について、広く国民の皆様からご意見をお聴きするため、平成28年3月25日(金)から4月23日(土)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
1.意見募集の背景
東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海においては、水質汚濁を防止し、当該海域の水質環境基準を確保するため、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法の規定に基づく第7次総量削減基本方針により、化学的酸素要求量(COD)、窒素及びりんに係る汚濁負荷の総量削減に取り組んでいるところです。次期総量削減基本方針の策定に向けては、平成27年12月7日付けで中央環境審議会から環境大臣に対して「第8次水質総量削減の在り方について(答申)」がなされました。
これを受けて、平成27年12月17日付け諮問第420号により中央環境審議会に対してなされた「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について(諮問)」について、平成28年2月より、中央環境審議会水環境部会総量規制基準専門委員会(以下「専門委員会」という。)において検討を行ってまいりました。
今般、平成28年3月22日に開催された専門委員会(第3回)において、本諮問に対する専門委員会報告案がとりまとめられました。本案について、広く国民の皆様からのご意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。専門委員会では、頂いたご意見を考慮し、報告案を最終的にとりまとめる予定です。
2.意見募集対象
・「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」(総量規制基準専門委員会報告案)
3.意見募集要領
(1)募集期間:平成28年3月25日(金)から平成28年4月23日(土)
(※郵送の場合は4月23日(土)必着とさせていただきます。)
(2)意見の提出方法:次のいずれかの方法でご提出ください。
① 電子政府の総合窓口(e-Gov)
電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームに記入の上、ご提出ください。
② 郵送、ファックス又は電子メールによるご提出
[意見提出様式]に従って提出してください。
提出先:環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5521-8319
FAX:03-3501-2717
(注意事項)
・ご意見は日本語でご提出ください。
・電話でのご意見の提出には対応いたしかねます。
・ご意見に対する個別の回答はいたしかねます。
・締切日までに未着の場合や記入もれ、趣旨が不明確なもの、意見募集対象以外のご意見等、本要領に即して記入されていない場合には、ご意見を無効扱いとさせていただくことがあります。
・頂いたご意見は、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、公表される可能性があります(公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えてください。)。ただし、ご意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合、及び法人等の財産権等を害するおそれがある記述がある場合には、該当箇所を伏せさせていただきます。
・なお、ご意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報は適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった本案に対する意見公募に関してのみ利用させていただきます。
4.資料の入手について
(1)インターネットによる閲覧
(2)窓口での配布
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階)
添付資料