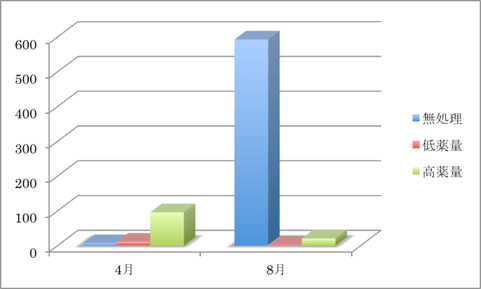沖縄でも台風が連続して接近し始め、朝夕の風が心なしか涼しくなり、空に浮かぶ雲の高度もあがったようにも思います。
そんなこんなで筆記試験も遠い過去になりつつありますが、身の回りで「来年の試験を受験しようと思っています」などというフレッシュな表明をちらほら受けるようになりました。
そんなひとには、まず今年の試験問題をチェックして、何をすべきか―合格するのに足りないもの―を知るべきだとアドバイスしています。
過去問の次にチェックしてほしいのは、やっぱり国交省白書ですね。
でもこれまで白書になじみのないいわば素人がいきなり読み始めてもきっと1ページくらいで睡魔に襲われるんじゃないかと思います。
白書の概要版みたいなのがあるといいのですが、とにかく事前に国の施策の大まかな方向性が頭に入っているといいですよね。
そんなことを考えていたところ、ちょうど国交省メルマガに、来年度の概算要求のポイントの記事がありました。
ここに書いてある方針を踏まえて白書を読むと頭に入りやすそうに思います。
しかもそれだけじゃなくって、この概算要求にあげられているひとつひとつが実は筆記試験の記述論文に設定される「課題」そのものなのです。
技術士第二次試験というのは、つまるところ概算要求に挙げられているようなさまざまな「課題」の達成を阻む問題点を抽出してその解決策を提案できる、そしてそれを論理的に記述できる能力が問われているのです。
ぜひこのなかから建設環境分野をピックアップしてそれについて考察を巡らせてみてください(あまりないかもしれませんけど)。
また、解答論文の実際の記述時にも使える言い回し(単語、センテンス、箇条書き)のネタ帳にもなっています。
というわけで、日常からなにげなしにこういった文言に触れておくと、来年あらためて勉強開始する時のスタートダッシュが図れる、といいますかアドバンテイジが得られているのではないでしょうか。
お勧めしたい練り上げ法として、この内容を頭に入れて会社の後輩のひとにでも口で説明してみるという方法があります。
現地調査に赴くときの移動中の車中なんかで会話がなくなったら、なにげに国の方向性の話を振ってみてレクチャーしてみてはいかがでしょうか。
とても身になる勉強方法だと思いますよ。
多少間違ったことを喋っちゃってもそれがかえって勉強になります。
間違いを発すると、その誤ち、そしてその正解は一生(は大げさですが)忘れなかったりしますからね。
では!
表参道【渋谷区神宮前】
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
■ ■ □ ■ ■■■■ 2013年8月27日 第1205号
■▼▼■ □ ■ ■
■ ▼ ■ □ ■ ■ 国土交通省メールマガジン
■ ■ □□□ ■ ■ いつもご利用ありがとうございます!
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
━ 目┃ 次┃ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━┛ ━┛
[1]新着情報
・本日の報道発表
・トピックス
・大臣会見要旨(8月21日)
・人事異動(8月27日)
・イベント・シンポジウム
・統計情報
[2]国土交通セミナー
平成26年度予算の概算要求のポイント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
──────────────────────────────
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[2]国土交通セミナー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎平成26年度予算の概算要求のポイント
【平成26年度予算概算要求の基本方針】
<全体方針>
・被災地の復興に取り組むとともに、防災・
済成長や生活向上の大前提である安全・安心の確保を図ります。
・我が国の成長実現に向け、国際競争力の強化、
した、
・要求に際しては、
の無駄を排除します。
<真に必要な公共事業予算の確保>
・公共事業予算は、平成25年度予算において、
めがかかりました。平成26年度予算においては、
課題にバランスよく対応するため、通常の要求及び「
優先課題推進枠」に係る要望を最大限活用し、対前年度比1.
望を行います。
<成長をもたらすストック効果の早期実現>
・インフラは完成してストック効果が発揮されて初めて、
や生活の向上を実感でき、また、
蓄積されたストックを戦略的に維持管理・更新し、
成間近のインフラの集中的な整備・完成を行うことなど、
ストック効果の早期の発揮を図ります。
<総合力の発揮>
・限られた財政資源の中で効率的なインフラの整備・運営・
民がサービスの質的向上を実感できるものとするため、
業への重点化を図るとともに、
やノウハウを積極的に活用します
・規制改革等と一体となって講じることにより、
出します。
【主な事業内容】
1.東日本大震災からの復興加速
・住宅再建・復興まちづくりの加速、事業の早期着手・
・インフラの復旧・整備(1,822億円)
・被災した公共交通の復興の支援
・被災地の観光振興(9億円)
・被災地におけるPPP/PFIの推進(2億円)
2.国民の安全・安心の確保
(1)防災・減災、老朽化対策
<災害発生時の応急活動の強化・充実>
・電子防災情報システムの構築及びTEC-
・気象等の監視・予測システムの強化(126億円)
・災害時の救援・緊急輸送能力等の向上(82億円)
<大規模地震に対して戦略的に推進する対策>
・公共施設の耐震化、津波対策等による強靱化の推進(1,
・代替性確保ネットワーク整備等の防災・震災対策(4,
・コンビナート港湾の強靱化の推進(2億円)
・鉄道施設の耐震対策に対する支援(82億円)
・老朽建築物の建替え、耐震改修等の促進(280億円)
・地下街の防災対策の推進(20億円)
<水害・土砂災害対策、渇水対策>
・大規模水害・土砂災害等に備えた治水対策、渇水対策の推進(
・地下水対策の推進(0.6億円)
<災害への対応力の強化>
・地籍整備による土地境界の明確化の推進(132億円)
・機動的な被害未然防止対策の強化(261億円)
<社会資本の戦略的な維持管理・更新>
・インフラ長寿命化の推進、点検・診断等の信頼性確保等(
・社会資本の戦略的な維持管理・更新の推進(3,731億円)
<防災・メンテナンス技術等によるイノベーション>
・電子防災情報システムの構築及びTEC-
・次世代インフラマネジメントシステムの構築(30億円)
<地域における総合的な事前防災・減災対策、
・地域における総合的な事前防災・減災対策、
的支援(防災・安全交付金)(12,227億円)
(2)公共交通等の安全・安心の確保
・高速ツアーバス事故等を受けた安全対策の強化(2億円)
・航空の安全対策の強化(4億円)
・海上交通、鉄道の安全対策の強化(4億円)
(3)戦略的海上保安体制の構築(459億円)
3.経済・地域の活性化
(1)国際競争力の強化等
<都市の国際競争力強化・人流の円滑化>
・大都市の国際競争力の強化のためのビジネス・生活環境整備(
・ITS技術を活用した円滑、安全・
・首都圏空港の機能強化(147億円)
・整備新幹線の着実な整備(822億円)
<強い経済の再生と成長を支える物流システムの構築>
・総合的な物流施策の推進(1億円)
・効率的な物流ネットワークの強化(2,037億円)
・港を核とした国際コンテナ物流網の強化(
深化と加速)(536億円)
・資源・
輸送網の形成)(43億円)
<競争力強化のための社会資本の総合的整備>
・競争力強化のための社会資本の総合的整備(
(10,558億円)
<民間投資の促進>
・PPP/PFIの推進(26億円)
<海洋の開発・利用・保全の戦略的な推進>
・海洋資源等の開発・利用の推進、
円)
<国際展開戦略>
・インフラシステム輸出等の推進(23億円)
(2)地域の活性化と豊かな暮らしの実現
<まちの活力の維持・増進(都市の再興)>
・
<人口減少・高齢社会、エネルギー問題等に対応するまち・
・スマートウェルネス住宅・シティの実現に向けた支援(
・超小型モビリティの導入促進(4億円)
・地域交通のグリーン化を通じた電気自動車の加速度的普及促進(
<公共交通の活性化>
・公共交通の充実(新たな制度的枠組みの構築、
(388億円)
・鉄道による地域活性化(136億円)
・空港の抜本的な能力向上(300億円)
<条件不利地域等の支援>
・離島、奄美群島、小笠原諸島等の条件不利地域の振興支援(
・「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」の形成推進(
<地域の活力を支える社会資本の総合的整備>
・地域の活力を支える社会資本の総合的整備(
(10,558億円)
<住宅・不動産市場の活性化、建設市場の環境整備>
・不動産市場の活性化のための環境整備(6億円)
・中古住宅流通・リフォーム促進等の住宅市場活性化(80億円)
・建設市場の環境整備等の推進(6億円)
(3)観光立国の推進
・訪日プロモーションの戦略的・重点的実施等(72億円)
・社会資本整備と一体となった観光振興
・
(11億円)
・国際会議等(MICE)の誘致・開催の促進(5億円)
■平成26年度国土交通省関係予算概算要求概要
http://www.mlit.go.jp/page/
──────────────────────────────