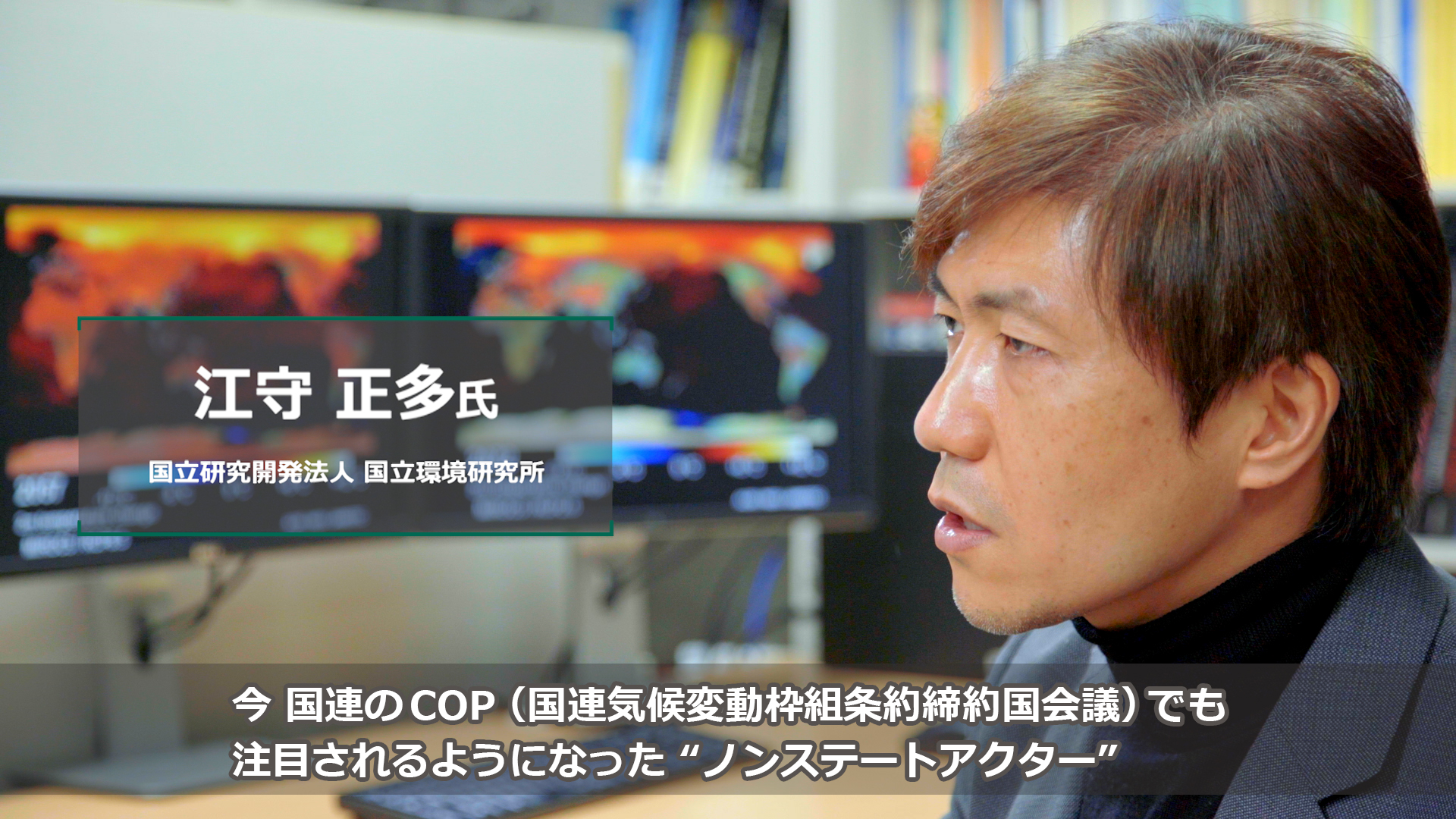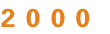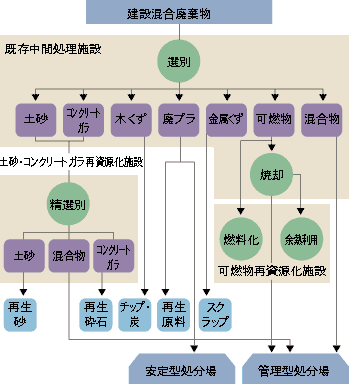デジタルを前提とした国土の再構築
~「国土の長期展望」最終とりまとめを公表します~
令和3年6月15日
国土審議会計画推進部会国土の長期展望専門委員会において、2050年を見据えた今後の国土づくりの方向性について検討を行い、結果をとりまとめましたので公表します。
コロナ禍も契機としたデジタル世界の到来は、地理的条件の不利に制約されてきた地方にとっては再生の好機となります。創意工夫によりデジタルとリアルを融合し地域に実装することで、地球環境問題等にも対応しながら、人口減少下であっても安心して暮らし続けられる多彩な地域・国土の構築を目指します。
【とりまとめのポイント】
1.国土づくりの目標 : 「真の豊かさ」を実感できる国土
2.目標実現に向けた三つの視点
(1)ローカルの視点 :「多彩な地域生活圏の形成」
・人々の行動範囲(通勤・通学等)である地域生活圏に着目
・遠隔医療やテレワークなどデジタル技術も活用することで、以前より少ない10万人前後の人口規模でも圏域の維持が可能(人口減少下で維持していくためには、国等による積極的な支援も必要)
⇒これにより大多数の国民が圏域内に含まれ、地域で暮らし続けることが可能に
・地域生活圏の実現に向け、住民目線に立って、[1]デジタル化の推進、[2]都市的機能等のリアルの充実、[3]「デジタル×リアル」の暮らしへの実装等の取組を推進(地域全体での果敢な取組が不可欠)
・地域生活圏単位で、良好な地域経済循環や分散型エネルギーシステムの構築を推進
・地域固有の歴史・文化・自然環境等を活かして、個性ある多彩な地域を全国に形成
(2)グローバルの視点 :「『稼ぐ力』の維持・向上」
<産業基盤の構造転換>
・大学等を核としたイノベーションの創出、そのための人材確保
・グローバルニッチや農業等の地域発のグローバル産業の育成 等
<大都市のイノベーション>
・成長率が低迷する東京等の大都市のデジタル化の徹底、知識集約型産業の集積促進による再生 等
(3)ネットワークの視点 :「情報・交通や人と土地・自然・社会とのつながり」
・国土の再構築の前提となる情報通信や交通ネットワークの充実
・「地域管理構想」の策定等を通じた地域住民自らによる国土の適正管理の推進
・防災・減災・国土強靭化による安全・安心な国土の実現
・「2050カーボンニュートラルの実現」に資する国土構造の構築
・個々人の価値観を尊重しつつ、支え合い、共感し合う共生社会の構築
3.今後の方向性 : 速やかに新たな国土計画の検討を開始すべき
(この機を逃さず、具体の施策につながるような実行性のある計画にすべき)
国交省HP:国土の長期展望専門委員会(※とりまとめ、懇談会の開催状況、資料等を掲載)
(URL)https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s104_choukitennbou01.html
添付資料
報道発表資料(PDF形式)